私と内視鏡との歴史
医学部生は5年生になるとポリクリ(Poliklinikの略)という臨床実習に入る。
消化器内科を回っているときだったかなな。内視鏡のシュミュレーションルームに連れていかれた。
箱の中に模型の胃や腸があり、箱の外の穴から挿入するというものだった。
ただ押し込むだけでは進めなく、引いたり、ひねったりする技術が必要とのことだった。
「時間のあるときに練習してみてくださいね」と指導医に言われたが、不器用な私がそのような高騰技術を使いこなせるとは思えず、さわることすらしなかった。
研修病院は家庭医コースのあるところを探した。
「今日はどうなさいましたか?」で始まる気楽に受診できるかかりつけ医。風邪、腹痛だけではなく、ちょっとした怪我、皮膚疾患にも気楽に対応できるだけではなく、できたら欧米のGeneral Practitionerと呼ばれる家庭医のように、正常分娩~看取りまで、いわばゆりかごから墓場まで関わりたかった。
家庭医コースのある見学先で、「よかったら、消化器内科も見ていってください」と言われ、大腸カメラ検査の見学を行った。まだ前処置薬(腸の中を空にするための洗腸剤)も今のように優れたものがなく、大腸に便があちこち付着していた。それを見て思わず吐きそうになった。
「私、消化器内科には絶対に行かない!」と見学先で叫んでしまった。
高校時代から医師になりたいと強く願っていながら長年実行に移せなかったのは、父親から強力に反対されたことが大きいが、血液や便に対して人一倍嫌悪感が強かったこともある。
そんな私が、医師になってからは、時には血が吹き出す中処置したり、前処置が十分でない大腸の便を飛ばしながら大腸検査をすることもあったりしている。
私が内視鏡業務に触れたのは、研修医2年目、消化器外科を回ったときだった。54歳で医師になり、足も悪い。しかも、感覚的にズレていて、オン・ザ・ジョブ・トレーニングには向かない性格。どの科でも、他の研修医とは違うプログラムが組まれ、担当患者さんも少なく、見学やレポートがメインの研修内容だった。
ところが消化器外科では、外来、入院から退院までの助手、手術の助手、カメラ持ちなどを担当させてくれた。内視鏡検査や処置は見学してレポートを書くように言われた。楽しい2ヶ月だった。
内視鏡見学の際、胃にヒダがあること、反転するとスコープが見えることを初めて知って、素人の友人に笑われたものだった。内視鏡に興味がわき、レポートを書くためと称して、「内視鏡診断のプロセスと疾患別内視鏡像・日本メディカルセンター」という本を上部消化管・下部消化管2冊と内視鏡検査全般について解説した本を買った。
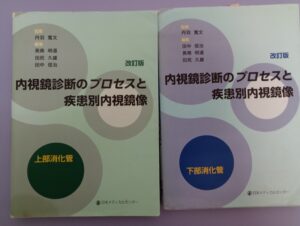 計3万円強。薄給の研修医としては、大きな出費だったが、その本は今も使っている。未来を予見していたのか?
計3万円強。薄給の研修医としては、大きな出費だったが、その本は今も使っている。未来を予見していたのか?
消化器外科に興味を持ち、後期研修の専攻は家庭医か消化器外科か大いに迷い、癌研にも中央病院、有明病院、東と3箇所見学に行った。癌研中央病院に見学に行ったとき、案内のお姉さんが、
「うちでは消化器外科を回ったとき、まずは内視鏡の訓練を行います。うちの医師は、胃カメラでは挿入してから抜去するまで5分で行います」と言う。
「おっすごいなあ。私もバリバリの外科医にはなれないだろうけれど、5分で胃カメラのできる医師になりたい。ここで訓練するのもいいなあ」と、癌研に憧れた。
結局のところ、「いくらなんでも無謀かな」と消化器外科には応募すらしなかった。時々、「無謀ついでに、いっそ消化器外科を専攻していても良かったかもしれないな」と後悔することはある。いずれにせよ、気楽に受診できるかかりつけ医+内視鏡医となったであろうけれど・・・。
ちなみに、今や、観察だけならば、胃カメラは挿入から抜去まで、5分どころか場合によっては3分以内に行っている。憧れが現実になったというところか!
結局、後期研修は岡山家庭医療センターで行うことになった。家庭医コースでは1年間、急性期病院で研修をする。岡山家庭医療センターでは津山中央病院というところで行うことになっていた。
津山中央病院は内視鏡業務が盛んであり、内視鏡が6台くらいあっただろうか?内科のコースでは、内視鏡業務もプログラムに組み込まれていた。研修医は内視鏡検査はすぐには施行できず、まずは洗浄を覚え、シュミレーターで練習してからデビューとなる。咽頭から食道に挿入するのに失敗すると、その日は見学のみになる。喉超えに成功すると、今度は十二指腸に挿入という難関がある。
「なんとか本格的に家庭医プログラムに入る前に、胃カメラくらいは通常観察ができるようになりたい」と強く思うようになった。本来なら、内科研修を終えたあとは、耳鼻咽喉科、産婦人科を回って、最後に小児科研修をすることになっていた。が、内視鏡へのこだわりもあり、それらをスキップして、残りの期間をすべて内科研修にあてた。今思えば、開業医をするにあたって、それらの科の研修をやっておきたかったな、と後悔する。結局、家庭医プログラムを中断して、あちこちで研修することになったのだから⋯ 人は近未来さえ、予見できないのだろう。
ところで、初期研修で腫瘍内科を回っていたとき、外部から来た先生に言われたものだった。
「君みたいな人がなぜ大学病院に来たの?君みたいな人は、何でもやらせてくれる徳洲会か、丁寧に指導してくれる民医連に行けばよかったのに~」
実際、医師4年目になろうとしているのに、飛行機の中で、「医師の方おりませんか?」と放送されても、なりを潜めていなければならないほどに、使い物にならない状態だった。家庭医になる前に普通の医師でありたい、と「なんでもやらせてくれる徳洲会」から転職先を選ぶことにした。徳洲会の医師人事担当の方と連絡をとり、「認定内科医を取りたい、思う存分内視鏡の訓練もしたい」と希望を伝え、結局野崎徳洲会病院に行くことにした。
「なんでもさせてくれる徳洲会」の噂にたがわず、ここで、研修医がやっておくべき手技のほとんどを体験・習得することができた。内視鏡もいきなり独立してすることになった。内視鏡医は一人だけで、「困ったら言ってね」と言われていたが、その先生は午前中だけで一人で10人以上を担当していた。
そういう状況の中、頻繁に助けを呼べるものではない。私は切羽詰まると力を発揮できるたちである。津山中央病院では喉超えもままならなかったのに、徳洲会にきてからは、胃カメラなら午前中で普通に7,8件をこなせるようになった。もっとも、初期のころは挿入してから抜管まで15分もかかり、ほとんどの方に鎮静薬なしで行ったので、そのころの患者さんには「ごめんなさい」と手を合わせたいところである。早期胃癌も発見できた。
胃カメラの技術は徳洲会で習得できたが、大腸カメラはなかなか習得できなかった。というのも、大腸はS状結腸と横行結腸が腹膜に固定されておらず、挿入しても進まず、腸がのびて患者さんに苦痛を与えることになるからだ。野崎徳洲会でも何度か挑戦させていただいたが、スコープの進行先がわからなかったり、腸がのびたりしてうまく行かなかった。一度、よそからバイトに来ていらっしゃった先生の指導のもとで奥まで到達したことがあって、手をたたいて喜んだものだった。
楽しく過ごした野崎徳洲会だったが、わけあって7ヶ月で去ることになった。内視鏡業務をさせてくれるところにと転職先にこだわった。
けれども、再びじっくり内視鏡検査に取り組めたのは、2014年、健和会病院に行ってからだった。転職前の面接で、「大腸カメラも習得したい」と話し、その希望をかなえてくださった。
当時の指導医の塚平先生(現健和会病院院長)は、「このブキ!(不器用者!の意)」と言いながらも最後まで見捨てなかった。最初の頃は大腸の奥まで到達すると、「やった!」と叫んでしまい、「そんなド素人みたいなことを言うな!」と怒られたものだった。ところで、医師4年目の頃から、内視鏡の専門医を取りたいという希望があった。健和会病院に専門医を取りたい旨を話すと難色をしめした。健和会病院の名誉のために言っておくと、意地悪をしたわけではなく、ほかの医師はどこかに研修に出て専門医を取っていて、院内で専門医をとった前例がなかったからである。
そんな折り、医師会の勉強会で昭和伊南病院の堀内先生と出会った。「内視鏡が大好きで、内視鏡で患者さんを救いたい」とおっしゃっていて共感した。プロポフォールを使った内視鏡検査を紹介され、「うちでは、内視鏡取得コースを開いています、研修したい方はどうぞ」とおっしゃった。最後の質問のときに、「私も行っていいですか?」と言うと、「どうぞ」と言って名刺をくださった。堀内先生は、生涯内視鏡センターで働くことを提案してくださったが、昭和伊南病院に転職する前に3年後開業する話が出ており、予定より1年早めて昭和伊南を退職して、1年間はバイトをしながら開業の準備をすることにした。
ところで勤務医時代は私のところには限られた症例しか回ってこなかったが、バイト先でも、現在開業した身でも内視鏡医は私一人である。結果的に、様々な症例を診ることになった。専門医試験で勉強しただけの症例、教科書にすらない症例にも遭遇して対応している。結局のところ、患者さんを診るとともに日々研鑽である。
ところで、当院では内視鏡検査目的で来られる方も多い。内視鏡検査は医師一人ではできず、検査補助業務のため、できるだけ二人以上の看護師がいたほうがいいのです。今、なんとかやりくりしている状態ですが、内視鏡技師の資格を持っている看護師さん、内視鏡業務に関心のある看護師さん、経験のある看護師さんにお手伝いいただけたらありがたいです。これを読んで興味のあるかたはぜひお問い合わせくださいね。

写真は最近デモをさせていただいたオリンパスの内視鏡です。常勤勤務医を離れてからは富士フィルムの内視鏡を使っていますが、内視鏡医訓練時代に使ったオリンパスの内視鏡に久しぶりに触れたこの機会に、私と内視鏡の歴史を振り返ってみました。

